両家へ結婚の挨拶を済ませると、結納もしくは両家顔合わせです。
イメージはあるものの、実は結納について詳しく知らないまま選んでいる人も多いのではないでしょうか。
顔合わせと違い、結納は当日の流れや挨拶、結納品や結納返しなど用意するものが決まっています。
本来は結納金の用意も必要ですが、結納金なしでも失礼にならない簡略化した形式もあるんですよ。
そこで、今回は結納の意味や結納をしない人の割合など、結納に関する基礎知識を詳しく解説します。
▼この記事に書いてあること
結納を正しく理解し、2人と両家の希望に合う形式を選ぶ材料にしてくださいね。
結納とは?意味を簡単に解説
結納とは、結婚を決めた2人と両家で金品を取り交わす、伝統的な婚約の儀式です。
結納:婚約成立のしるしに、両当事者かその親が金銭または品物を取り交わすこと。また、その儀式や金品。 引用元:Weblio辞書-「結納」の意味や使い方 わかりやすく解説-デジタル大辞泉
結納を執り行うことには、大きく2つの意味合いがあります。
- 婚姻の約束を、2人だけの口約束からより公なものにする
- 婚姻による両家の新たな結びつきを祝福する

新たな結びつきを祝う儀式であることから「結び納める」と書いて、「結納(ゆいのう)」という読み方なんですね。
もともと、嫁をもらう男性側が相手側への感謝や礼節の気持ちを形にした儀式ですので、男性側から女性側へ金品を贈るのが基本的な形式です。
婿入りの場合だと、男女が逆になるため、女性側から男性側へ金品を贈る形式に変わります。
結納と顔合わせの違いは?
入籍前に両家が一堂に会する場として、両家顔合わせがあります。
儀式としての意味合いが強い結納に比べると、顔合わせは両家の交流に重きを置いたカジュアルな食事会であるのが、最も大きな違いです。
▼結納と顔合わせの違い
| 結納 | 顔合わせ | |
|---|---|---|
| 目的 | 婚約を正式なものとする | 両家の親睦を深める |
| 金品取り交わし | あり | なし |
| 服装 | 正礼装・準礼装・略礼装 | 準礼装・略礼装 |
| 当日の流れ | 決まっている | 自由 |
結納は古くから続いてきた、婚姻による家と家との関係性を結ぶ儀式です。
結納と顔合わせのどちらにするかは2人だけで決めることではなく、必ず両家の意向を確認して選びましょう。

最近では、形式にこだわらないカジュアルな顔合わせが人気ではあるものの、地域やご家族の考え方から結納の形式を大切にする文化も根強く残っています。
結納しないorする|最近はなしが多いの?
伝統的な儀式とはいえ、結納をするorしないは、家庭ごとに考え方も異なるため、悩ましいところです。
最近では顔合わせが主流ですが、実際の割合はどのくらいなのでしょうか。
▼結納・両家の顔合わせの実施状況(全国平均)
| 両方行った | 6.9% |
|---|---|
| 結納のみ行った | 2.5% |
| 両家の顔合わせのみ行った | 80.2% |
| どちらも行わなかった | 10.3% |
| 無回答 | 0.1% |
引用元:リクルートブライダル総研-ゼクシィ結婚トレンド調査 2022
過去5年間のアンケートを見比べても、「結納はせず、両家の顔合わせのみ行う」の割合が高いと分かります。
| 両家の顔合わせのみ | 結納のみ | |
|---|---|---|
| 2018年 | 80.9% | 3.4% |
| 2019年 | 82.6% | 2.9% |
| 2020年 | 84.7% | 2.4% |
| 2021年 | 83.5% | 2.8% |
| 2022年 | 80.2% | 2.5% |
引用元:リクルートブライダル総研-ゼクシィ結婚トレンド調査 2018 ゼクシィ結婚トレンド調査 2019 ゼクシィ結婚トレンド調査 2020 ゼクシィ結婚トレンド調査 2021 ゼクシィ結婚トレンド調査 2022

8割以上が両家顔合わせを選び、結納をする人はきわめて少数なので、最近は両家顔合わせが主流になっていることがよく分かります。
結納金の相場とは?お金の使い道も
「ゼクシィ結婚トレンド調査2022」によると、結納金の金額は全国平均で98.8万円という結果が出ています。
結納金は50万~100万円の金額の中で用意するのが一般的ですが、その中でも100という数字はキリが良く、縁起が良いことからも選ばれやすい金額です。
▼結納金に選ばれる金額と避けられる金額
| 金額 | 理由 | |
|---|---|---|
| 選ばれる金額 | 50万・70万 | 割り切れない数は縁起が良い |
| 80万 | 8が「末広がり」を意味する | |
| 100万 | 「一包み」と呼ぶ縁起の良い数 | |
| 避ける金額 | 60万円 | 割り切れる数は「別れ」を連想させる |
| 90万円 | 9が「苦しむ」を連想させる |

では結納金は、誰が払うのが一般的なのでしょうか。

結納金は嫁入り準備の支度金として、女性側の家に贈るものですので、男性本人もしくは男性の親が払います。
男性側から贈られた結納金の受け取り手は、女性本人ではなく女性の親となり、結納金の使い道まで決めるのが一般的です。
結納金はあくまで、嫁入り準備の支度に充てる費用ですので、親が自分たちに使うことや新婚旅行の費用として使うのは、本来の目的と異なります。
結納金に税金はかかる?
お金の授受となると、気になるのが「税金」です。
本来であれば、個人から贈与により財産を取得した場合には「贈与税」が発生します。
ですが、社会通念上相当な額で、正しい目的に使われている場合、下記のように贈与税がかからない財産に該当すると考えられ、結納金に税金はかかりません。
8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの 引用元:国税庁-No.4405 贈与税がかからない場合

国税庁では財産の性質や贈与の目的からみて、贈与税がかからない財産を例を掲げて認めているんですね。
結納金なしは失礼で激怒される!?現在の風習とは
結納金の用意は、「正式結納」と「略式結納」と呼ばれる2つの形式のどちらで執り行うかによって異なります。
結納品を省略できる「略式結納」であれば、結納金を準備しなくても失礼になりません。
一方、最も格式の高い「正式結納」の場合、全ての結納品を用意する必要があるため、結納金が必要です。
結納のイメージとして、両家が結納品を挟んで一堂に会している場面が連想されますが、このイメージは「略式結納」の形式です。
「ゼクシィ結婚トレンド調査2022」では、仲人の有無に関するアンケートで95.5%が「仲人を立てなかった」と回答しており、結納の主流は「略式結納」となっています。
略式結納が主流ではあるものの「結納金を用意しなかった」と回答したのは6.1%で、大多数が結納金を準備しています。

結納金なしの場合、贈る側から提案すると悪い印象を与える可能性も……あくまで受け取る側から提案する形がいいですね。
結納金のお返し(結納返し)とは?
女性側から男性側へ贈る結納品のお返しを「結納返し」と呼びます。
本来は結納のように結納品一式を贈りますが、略式結納が主流となっている背景から、結納返しも簡略化、もしくは結納返しなしのパターンも。
そこで、結納返しに関する代表的な質問についてまとめました。
| 結納返しの品物は時計? | ・時計でなくてもOK ・腕時計やスーツが代表的 |
|---|---|
| 結納返しはいつ行う? | ・結納後、日を改めて ・結納と同日に交換 ・新居へ荷物を運び入れるとき |
| 結納返しは誰が払う?両親? | ・女性側の両親が支払う |
| 結納返しの金額は? | ・現金:46.2万円※1 ・品物:21.2万円※1 結納金の2~5割程度が相場 |
| 関西や九州ではルールが違う? | 結納のルールは地域によって異なる ・「関東式」 結納返しあり ・「関西式」 結納返しなし ・「九州式」 結納返しなし |
※1 引用元:リクルートブライダル総研-ゼクシィ結婚トレンド調査 2022

地域によるルールの違いとは、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。
「関東式」「関西式」「九州式」の3つの違いによって異なる点は4つです。
- 結納品の名称
- 結納品の数
- 結納品の飾り方
- 結納返しの有無
男性側も女性側も同格と考える「関東式」には結納返しがありますが、「関西式・九州式」では、男性側だけが贈るものと考えられているため、結納返しの文化はありません。
結納品セットとは|略式セットの飾り・品物は?
結納品は正式な形式だと9品ですが、地域によっては9品以上揃えるところもあります。
いずれの結納品も夫婦円満・子宝など、一つひとつに意味が込められた縁起物です。
| 関東式 | 関西式 |
|---|---|
| 1.熨斗(のし) 2.寿栄廣(すえひろ) 3.御帯料(おんおびりょう) 4.家内喜多留(やふなぎだる) 5.友白髪(ともしらが) 6.寿留女(するめ) 7.子生婦(こんぶ) 8.勝男武士(かつおぶし) 9.目録 |
1.熨斗(のし) 2.寿栄廣(すえひろ) 3.小袖料(こそでりょう) 4.家内喜多留(やふなぎだる) 5.高砂 6.寿留女(するめ) 7.子生婦(こんぶ) 8.松魚料(しょぎょうりょう) 9.結美和(ゆびわ) |
関東式は目録を含めた9品となっているのに対し、関西式は目録を含めない9品となっています。
必要な結納品をまとめた結納セットは、専門店や百貨店、ECサイトで購入可能で、関東式・関西式を選べる場合がほとんどです。
▼関東式 結納セット
| ブランド名 | 結納屋さん.com |
|---|---|
| 参考価格 | 74,510円 |

結納会場によっては、結納品セットと当日の飾りつけも任せられる結納プランがあるので、慣れない準備でも手間がかからず人気を集めています。
結納品を簡略化する場合、縁起の良い割り切れない品数で用意します。
最近は簡略化したセットを取り扱う店舗がほとんどですので、希望の品数に合わせて選ぶことが可能です。
▼略式結納セット
| ブランド名 | 結納屋さん.com |
|---|---|
| 参考価格 | 11,175円 |

結納品は最も少なくすると3品ですが、ほかにも5品・7品と選べるようになっていますよ。
結納品は処分しても問題ない?
縁起物である結納品は、結納が終わったら処分していいものなのか迷うところです。
結論からお伝えすると、処分するタイミングを守れば、結納品を処分すること自体に何も問題はありません。
結納品を処分する方法は、主に3つです。
- お寺や神社でお焚き上げ・清祓いをおこなう
- ごみに出す
- 兄弟に譲る
贈り物・縁起物である結納品をそのまま捨てるのに抵抗がある場合は、お寺や神社にお焚き上げや清祓いを依頼するのがいいでしょう。

相手側への礼儀を考えても、お炊き上げや清祓いをして丁寧な処分を心がけたいですね。
可燃ごみとして捨てる場合、塩をふって清めてから、白い布や紙で包んで、他のごみと分けて捨てましょう。
一部の地域では、仲の良い夫婦の結納品は縁起が良いとされる「福分け」という風習があり、兄弟で結納品を使いまわすこともあります。
ただし、結納品は使いまわさず新しく用意するのが一般的ですので、風習に理解がない場合の使いまわしは失礼にあたり、注意が必要です。
結納の受書・目録・記念品とは?
結納品とともに受け渡しをする書類に、「目録(もくろく)」「受書(うけしょ)」があります。
この2つの書類はいわゆる、結納品に関する「納品書」と「受領書」です。
▼「目録」と「受書」の記載内容
- 結納品の名称
- 数量
- 日付
- 名前
目録であれば「結納の品をお納めください」、受書であれば「確かに受取りました」という意の一文を最後に添えます。
また、結納の記念品となる「婚約記念品」は結納金の代わりとして用意されることが多いですが、婚約記念品を結納金に加えて用意してもかまいません。

婚約記念品は、男性からは婚約指輪、女性からは腕時計などを選ぶのが定番です。
結納の服装は?女性&50代母親の服装も
結納の場では、女性は振袖、母親は着物を着ているイメージがありますが、結納の形式によって、当日着るべき服装は若干異なります。
どちらの形式においても、最も大切なポイントは、両家で格式の揃った服装を着ることです。
| 正式結納 | 略式結納 | |
|---|---|---|
| 女性 | ・振袖 | ・振袖 ・訪問着 ・ワンピース |
| 男性 | ・紋付き羽織袴 | ・ブラックスーツ ・ダークスーツ |
| 母親 | ・黒留袖 ・色留袖 |
・色留袖 ・訪問着 ・アンサンブル ・ワンピース |
| 父親 | ・紋付き羽織袴 ・モーニング |
・ブラックスーツ |
最も格式の高い正式結納では、服装も正礼装で合わせますが、略式結納の場合は、準礼装・略礼装から服装を選びましょう。
女性や母親が洋装を着る場合、喪を連想させるような黒ではなく、明るい色合いを選ぶのがおすすめです。

50代の母親であれば、あまり着慣れない着物よりもアンサンブルやワンピースがいいでしょう。
結納の金額!準備にかかるトータルの相場は?
ここまで、結納をおこなうにあたり、結納金や結納品の用意が必要だとお伝えしてきました。
結納の準備費用の中で大部分を占めるのが結納金ですが、必要費用をトータルすると、どのくらいの金額が必要になるか確認しておきましょう。
▼結納に関する費用まとめ
| 全国平均 | |
|---|---|
| 結納式の費用 | 16.6万円 |
| 結納金 | 98.8万円 |
| 結納品 | 10.8万円 |
| 結納返し | 46.2万円(現金) 21.2万円(品物) |
引用元:リクルートブライダル総研-ゼクシィ結婚トレンド調査 2022
結納返しを除く、結納品に関する費用の合計金額は約126.2万円です。

結納金の相場が約100万円ですので、結納金の金額次第でトータルの金額にも大きく差が出そうですね。
結納の流れを紹介
結納は、婚約の儀式として決まった一連の流れがあり、内容としては、結納品の取り交わしがメインです。
今回は、略式結納(関東式)の流れをご紹介しますが、結納返しをしない関西式や九州式の場合、さらに簡潔になります。
結納では、上記の通り「結納品を納める・目録を確認する・受書を渡す」を両家で繰り返します。

滞りなく進んだ場合、結納自体の所要時間は約20分ほどですので、意外とあっという間に終わってしまいますよ。
結納の挨拶・口上まとめ【例文あり】
結納の特徴として、流れの中で使う「口上」という決まり言葉があります。
口上は日常的に使う機会のない言い回しですが、難しい言葉ではありませんので、可能であれば覚えて臨みたいものです。
結納の流れの中で必要な、挨拶と口上のタイミングは3つあります。

ここでは、仲人を立てない略式結納での挨拶や口上の例文をまとめていますので、参考にしてくださいね。
はじまりの挨拶
両家が部屋へ入場し、着席が済んだタイミングで、まずは結納を始める挨拶をおこないます。
はじまりの挨拶は、基本的に男性の父親がおこないますが、父親がいない場合は母親もしくは男性本人がおこないます。
▼男性の親/家主体
このたびは●●家のご長女・●●様と、私どもの長男・〇〇との縁談をご承諾くださいまして、感謝申し上げます。
本日はお日柄もよろしく、これより結納の儀を執り行わせていただきます。
▼男性の親/本人主体
このたびは●●様と、私どもの〇〇との縁談をご承諾くださいまして、ありがとうございます。
本来ならば仲人様をお通しするのが正式ではありますが、本日は略式にて結納の儀を執り行わせていただきます。
▼男性本人
このたびは●●様との縁談をご承諾くださりまして、誠にありがとうございます。
本日はお日柄もよろしく、これより結納の儀を執り行わせていただきます。
挨拶や口上は、家を主体とした結納なのか、本人を主体とした結納なのかで、やや言い回しが異なります。

お互いの家を主体とするのか、結婚する2人を主体とするのかによって、言い回し以外に当日の席順も変わりますので、事前に決めておきましょう。
挨拶自体は短く簡潔なものですが、慣れない言い回しによる緊張感もあるはずです。
結納の始まりを告げる挨拶ですので、ゆっくりハキハキと話しましょう。
結納品・受書の取り交わし
はじまりの挨拶が済んだら、男性側から女性側へと結納品を納めます。
結納品・受書の取り交わしでは、納める側と受け取る側がそれぞれ口上を述べます。
内容としては「結納品を納めます」「結納品を受け取りました」というものだと、頭に入れておきましょう。
1.結納品を納めるとき
〇〇家からの結納の品でございます。幾久しくお納めください。
こちらは〇〇からの結納の品でございます。幾久しくお納めください。
私どもからの結納の品でございます。幾久しくお納めください。

「幾久しく(いくひさしく)」は、「いつまでも変わらずに、末永く」という意味があります。
2.結納品を受け取るとき
ありがとうございます。幾久しくお受けいたします。
3.受書を渡すとき
●●家からの受書でございます。幾久しくお納めください。
●●からの受書でございます。幾久しくお納めください。
4.受書を受け取るとき
(受書の内容を確認して)相違ございません。幾久しくお受けいたします。
ここまでが、結納品・受書の取り交わしの一連の流れです。
結納返しをおこなう場合は、ここまでと同じように女性側から男性側へと結納返しを納めます。
結納返しの口上にほとんど変わりはなく、男性側へ結納返しを納めるときの一言が少し異なる程度です。
5.結納返しを納めるとき
●●家からの結納返しの品でございます。幾久しくお納めください。
気持ちばかりではございますが、御礼の品を用意いたしました。幾久しくお納めください。
結納返しの口上に対する返事や、その後の流れ・口上は特に変わりません。
結びの挨拶
結びの挨拶も、はじまりの挨拶と同様に男性の父親がおこないます。
結納が無事に済んだことへの感謝の気持ち、両家の付き合いについてのお願いを伝えて、結びの言葉とします。
▼男性の親
本日は誠にありがとうございました。
おかげさまで無事に結納をお納めすることができました。
今後とも幾久しくよろしくお願いいたします。
▼女性の親
こちらこそありがとうございました。
今後とも幾久しくよろしくお願いいたします。

口上は、必ずしも一言一句覚えておく必要はないので、言いやすい言葉に変えて自分なりの挨拶を伝えてもいいですね。
不安であれば、メモ書きを見ながらの挨拶・口上でも構いませんので、結納を執り行うことへの感謝や婚約を喜ぶ気持ちをしっかりと伝えるようにしましょう。
結納の手土産は必要?
結納を執り行う上で、手土産を用意する決まりはありませんが、相手への礼節として用意しておくと丁寧です。
もともと、結納における「手土産」とは男性側が女性側の家を訪問する際に、感謝の意を表すために用意するものでした。
女性側から男性側へ訪問のお礼として渡すものは「引出物」と呼ばれます。
最近は、自宅に赴いて結納をおこなうことは少なくなりましたが、「手土産・引出物」の文化は残っており、結納に手土産を用意する人は多いようです。

手土産を用意する場合は、両家で金額に差が出ないようにだいたいの予算を決めておきましょう。
まとめ
ここまで、結納の意味や結納をしない人の割合など、結納に関する基礎知識を詳しく解説しました。
- 結納とは、結婚を決めた2人と両家で金品を取り交わす婚約の儀式
- 最近では結納はせず、両家顔合わせが主流
- 結納金は、100万円が相場
- 略式結納であれば、結納金なしでも失礼にならない
- 結納のルールは「関東式・関西式・九州式」と地域で分かれている
- 地域によって異なる点は、結納品の名称や結納返しの有無
- 略式結納での服装は、準礼装か略礼装
- 結納返しを除き、結納にかかる費用の相場は約126.2万円
- 結納は一連の流れが決まっている
- 挨拶や口上を述べる内容とタイミングにも決まりがある
- 手土産はなくても問題ないが、用意があると丁寧
近年は、形式にこだわらないカジュアルな両家顔合わせが主流となり、結納をおこなう人は少数派です。
とはいえ、婚約の儀式である結納は、家と家との新たな結びつきを祝福し、婚姻の約束を確かなものとする重大な役割を担っています。
顔合わせに比べ緊張感はあるものの、古くから続けられてきた日本独自の伝統的な儀式で、結婚への第一歩を迎えてみてはいかがでしょうか。

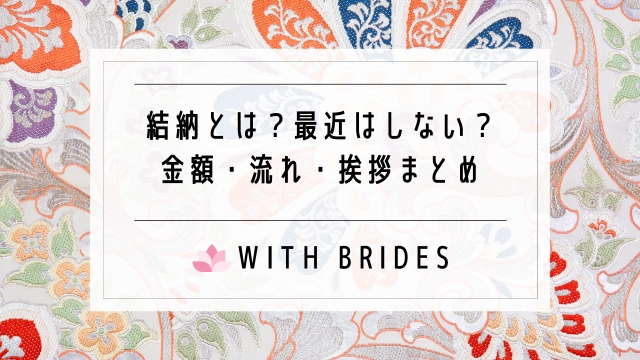






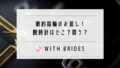




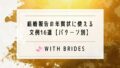
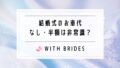


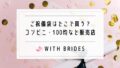


































コメント